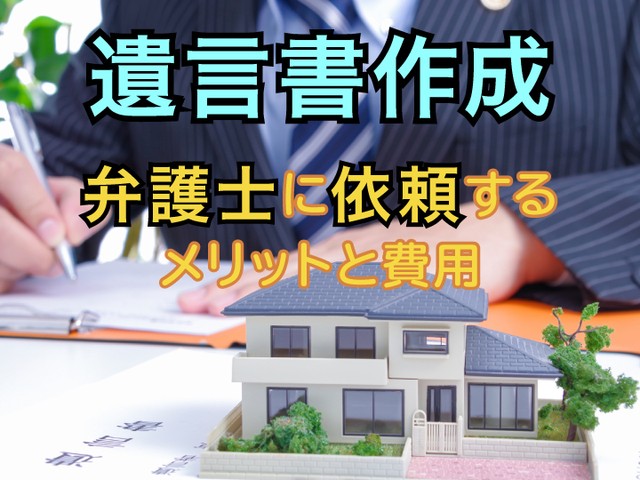更新日:
公開日:
遺言書作成の弁護士費用の相場は? 依頼のメリットや注意点も解説
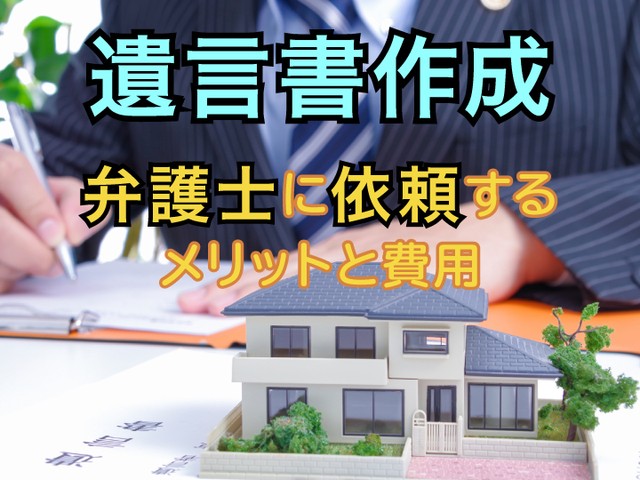 弁護士に依頼することで、遺言書を確実に作成しましょう。
弁護士に依頼することで、遺言書を確実に作成しましょう。
遺言書作成を弁護士に依頼することで、遺言書が要式不備で無効になったり、その内容を巡って相続人が争うような事態を防ぐことができます。
遺言書作成の弁護士費用は10万円から20万円が目安です。特殊な条項が盛り込まれる場合には50万円を超えるケースもあります。安い費用ではありませんが、メリットを踏まえた上で弁護士のサポートを受けることを検討するとよいでしょう。
今回の記事では、相談から遺言書作成、保管、遺言執行まで弁護士に依頼した場合にかかる費用の相場をまとめてご紹介します。
遺言書の相談ができる弁護士を探す
北海道・
東北
関東
甲信越・
北陸
東海
関西
中国・
四国
九州・
沖縄
1. 弁護士・法律事務所に遺言書作成を依頼するメリット
弁護士に遺言書の作成を依頼するメリットは、主に次の5つです。
- 相談から死後のトラブル対応までワンストップで対応可能
- せっかくの遺言書が無効にならない
- 相続トラブル予防
- 万が一の場合でも、スムーズにトラブル解決
- 遺言執行の依頼も可能
それぞれについて説明します。
1-1. 相談から死後のトラブル対応までワンストップで対応可能
弁護士は、遺言書の作成だけではなく遺言執行や遺産相続トラブルの解決まで対応できる専門家です。弁護士に相談すれば、遺言書作成、保管、遺言執行、死後のトラブル回避や解決まで、およそ相続税以外の手続きをすべて任せられるので安心できるでしょう。
1-2. せっかくの遺言書が無効にならない
遺言書には厳格な要式があります。自分で作成する「自筆証書遺言」の場合、財産目録を除く全文(タイトルや日付、氏名を含む)を自筆で書き、押印しなければなりません。訂正する場合にも厳格なルールがあります。
自分で作成すると、不備が発生して無効になってしまうリスクが高くなります。弁護士に依頼すれば、依頼者の要望を聞き取った上で、法的に正しい内容の遺言書の原案を作成してくれます。原案を参考に自筆証書遺言を作成する際には形式面の不備がないかを改めて確認してもらえるので、要式不備で無効になる可能性はほぼありません。
1-3. 相続トラブル予防
世間では、遺言書がもとで相続トラブルになるケースが多々あります。たとえば、「長男にすべての遺産を相続する」といった不公平な内容だった場合です。また、内容があいまいな場合もその解釈を巡って、トラブルになることがあります。
弁護士に依頼すれば、財産調査を行った上で財産目録を作成し、遺留分や相続人との関係性を考慮したうえでトラブルを防止するための具体案を検討してくれますので、死後の相続トラブルを予防しやすくなります。
1-4. 万が一の場合でも、スムーズにトラブル解決
遺言書を巡ってトラブルが起きると、当事者同士の話し合いでは感情的になって解決策がなかなか見いだせないことがよくあります。そのような場合でも、弁護士が間に入って交通整理をすれば比較的スムーズに解決しやすいものです。親族同士で何年も争い続ける悲劇を避けやすくなるでしょう。
1-5. 遺言執行の依頼も可能
遺言書の作成だけでなく、遺言執行者としての役割を弁護士に依頼することもできます。遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者です。遺言の執行には、各金融機関での手続きや法務局での相続登記などの対応が必要で、かなりの手間がかかります。
また、遺言の内容によっては、遺言執行者がいないと実現できないこともあります。遺言書の内容をよく理解した弁護士に遺言執行者を任せることによって、遺言の内容をスムーズに実現できるでしょう。
2. 遺言書作成にかかる弁護士費用相場
弁護士には遺言書の作成や遺言執行を依頼できます。相談、作成、保管、執行に分けて弁護士費用の相場をみていきましょう。
2-1. 相談費用(目安:1万円)
弁護士に遺言書作成を相談すると、相談料がかかります。相場としては30分5000円(税別)。だいたい1時間分の1万円(税別)程度、用意しておけば良いでしょう。なお、依頼後は相談料がかからなくなるので、相談料が必要なのは依頼前の1回と考えておけば大丈夫です。ただしこれは初回に依頼したケースです。
また、初回相談は無料で対応してくれる弁護士事務所もたくさんあります。
2-2. 遺言書作成費用(目安:10万~20万円)
遺言書を作成すると、作成手数料がかかります。遺言内容や遺産額にもよりますが、定型的な遺言書であれば、相場としては10万円から20万円程度と見ておいてください。
ただし、遺産に様々な種類の財産が含まれていて評価が難しかったり、相続人の関係が複雑だったり、二次相続対策などを盛り込んだりする非定型のケースでは50万円を超える可能性もあります。
下記は、日本弁護士連合会がかつて定めていた弁護士費用の目安「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」です。今も参考にしている弁護士も多く、相場の目安となっています。
| 遺言書の作成 |
定型 |
10万円~20万円 |
| 非定型 |
経済的な利益の額(遺産の額)が
・300万円以下:20万円 |
| ・300万円超3000万円以下:経済的利益の1%+17万円 |
| ・3000万円超3億円以下:経済的利益の0.3%+38万円 |
| ・3億円超:経済的利益の0.1%+98万円 |
| ※複雑/特殊な事情がある場合、弁護士と依頼者の協議で定める |
| 公正証書遺言 |
上記の金額に3万円を加算 |
もっとも、弁護士費用はそれぞれの法律事務所が自由に決めることができるため、依頼前に見積もりを依頼するなど事前に確認して下さい。
2-3. 遺言書保管費用(目安:1万円)
作成した遺言書は自宅で保管しておくこともできますが、紛失などの恐れがあります。そうしたリスクを避けるために、弁護士に預けることができます。保管費用は、法律事務所によって様々ですが、年間1万円前後が多いです。
2-4. 遺言執行にかかる費用(30万円~)
弁護士に「遺言執行者」への就任を依頼すると、費用が発生します。遺言執行者は預貯金の払い戻しや不動産登記などを行います。遺言執行者への就任を依頼した場合、最低でも30万円程度はかかると考えてください。
業務内容が多岐にわたるケースや遺産が多い場合などには増額され、状況によっては100万円を超える可能性もあります。
2-5. その他の費用
現地調査を行うために出張が必要となる場合などには、日当や交通費が必要です。交通費は実費、日当は日額3~5万円程度となるでしょう。
また公正証書遺言を作成する時には、公証役場に払う「実費」がかかります。こちらは公証人の手数料ですので、自分で公正証書遺言の作成手続きをする場合にも必要です。金額は遺産額によって異なりますが、数万円(10万円以下)となるケースが多いでしょう。
3. 弁護士と一緒に遺言を作成する流れ
弁護士に遺言書の作成を相談・依頼する場合の一般的な流れは下記のとおりです。
3-1. 初回の面談
まず初回の面談で、弁護士が遺言者の家族構成などの事情、希望などを聞き取り、遺言書の内容や書き方などをアドバイスします。必要に応じて弁護士に依頼するメリットや費用も説明します。
3-2. 2回目以降の面談|遺言書の原案を弁護士が作成
依頼を受けた場合は改めて面談し、より詳しい事情を聞きます。遺言者の希望に基づき、弁護士が相続財産目録を作成し、遺言書の原案を作成します。その後、原案を遺言者に確認してもらい適宜、加筆・修正します。
遺言書の内容が確定したら作成に取り掛かります。「自筆証書遺言」であれば、弁護士が作成した原案に沿って、遺言者に手書きで遺言書を書いてもらい、弁護士が内容や形式に問題がないかをチェックします。
なお、遺言書には自筆証書遺言のほかに、「公正証書遺言」があります。法的な効果は同じですが、自筆証書遺言は財産目録を除く全文を自筆で書くのに対し、公正証書遺言は公証役場で公証人が作成します。費用は手間はかかりますが、自筆証書遺言と比べて無効になるリスクが小さい、家庭裁判所の検認手続きが不要になる、紛失のおそれがないなどのメリットがあります。
公正証書遺言作成のサポートについても、弁護士が原案を依頼者の要望に添って作成する点では同じです。原案を作成したら、弁護士が公証役場に公正証書遺言の作成を依頼し、公証人との間で細かい内容を調整していきます。必要に応じて証人の手配も行います。調整が完了したら遺言者が実際に公証役場に行って、公正証書遺言を作成します。当日は弁護士も立ち会います。
3-3. 遺言完成とその後のサポート|遺言保管と遺言内容の実現
自筆証書遺言は自分で保管することになりますが、紛失するリスクがあります。
そのため、希望があれば弁護士が保管をします。必要に応じて定期的に遺言者に手紙や電話で連絡をして、状況の確認をします。財産の変動や意向の変化などにより遺言書を作成し直す必要がないか、遺言者が亡くなっていないかなどを確認するためです。
なお、自筆証書遺言は申請すれば、法務局で保管する制度があります。また、公正証書遺言の場合、原本は公証役場で保管されます。
遺言者が亡くなった後、弁護士が遺言執行者に指定されている場合、遺言内容の実現に向けて手続きを進めます。
4. 遺言書作成における、弁護士と他の専門家の違い
遺言書作成の支援ができる専門家には弁護士以外に「行政書士」があります。遺言について相談に応じている「司法書士」もいます。弁護士とこれらの士業とでは、何が異なるのでしょうか。
4-1. 行政書士や司法書士には「代理権」がない
行政書士や司法書士と弁護士の一番の違いは「本人の代理人になれるかどうか」です。弁護士は本人の代理人として交渉や調停、裁判などが可能です。
一方、行政書士には一切の代理権が認められません。依頼できるのは書面作成だけです。司法書士の場合、国から認められた「認定司法書士」であれば「140万円以下の紛争」についてのみ代理権がありますが、それを超える金額の紛争は代理できません。遺産分割調停の代理権も認められません。
遺産相続トラブルでは、140万円を超える紛争となるケースがほとんどでしょう。死後に紛争になった場合、対応できるのは弁護士のみとなります。
4-2. 弁護士費用が高い理由
遺言書作成費は弁護士費用が10万~20万円ほどかかるのに対し、司法書士や行政書士の費用は安くなるのが一般的です(ただし事務所によります)。例えば、行政書士の費用はおおむね10万円です。これは、弁護士は紛争対応が可能なのに対し、行政書士や司法書士には対応できないからです。
4-3. トラブルの恐れがあるなら、 当初から弁護士に依頼した方が良い
費用が安いからといって行政書士などに対応を依頼しても、トラブルになったら改めて弁護士に相談しなければなりません。結局二重払いになって費用が高くなるでしょう。トラブルになる可能性があるなら、最初の段階から弁護士に依頼するのが得策といえます。
5. 弁護士に遺言書を作成してもらう時の注意点
5-1. 希望をしっかり伝える
弁護士に遺言書を作成してもらうときには、自分の希望をしっかり伝えることが大切です。遺言書においてもっとも重要なのは本人の意思だからです。いくら専門家とはいっても、家族の内情まではわかりません。ご本人がしっかり希望を伝えてこそ、弁護士側もベストな対応ができるのです。
懸念される問題を事前に伝えておけば、効果的にトラブルを予防できる内容の遺言書にしてもらえますし、万一の場合にはスピーディに対応してもらえるでしょう。
5-2. もめそうなケースでは当初から弁護士に依頼する
遺言書作成を専門家に依頼しようとするとき、費用の安い行政書士事務所などに目が向くかもしれません。しかし死後にもめそうな場合、当初から弁護士に依頼する方が結局コストを抑えられる可能性が高くなります。
特に下記のようなケースでは、当初から弁護士に相談したほうがよいでしょう。
- 遺産に不動産が含まれている
- 相続人同士が不仲で、もめる恐れがある
- 生前贈与を受けた子どもがいる
- 前婚の子どもや認知した子どもがいる
6. 遺言作成に強い弁護士・法律事務所の選び方
遺言書作成を成功させるには、遺産相続に精通した弁護士選びが不可欠です。弁護士には専門分野や経験の差があるため、以下のポイントに注目して選びましょう。
- 相続案件の実績は豊富か
- 費用は明確か
- 要望に耳を傾けてくれるか
- 説明は丁寧でわかりやすいか
- 相性はいいか(話しやすいか)
- 事務所の対応・レスポンスは早いか
- ほかの仕業(税理士など)と連携しているか
初回の無料相談を活用し、複数の事務所に足を運んで、上記の点を比較するとよいでしょう。
7. 遺言書作成を弁護士に依頼することに関連して、よくある質問
Q. 相続税対策も踏まえた遺言書を作成したいのですが、弁護士への相談で大丈夫でしょうか
相続税の専門家である税理士に相談するとよいでしょう。税理士と連携している弁護士に依頼すれば、法的な正しさだけでなく、相続税まで配慮した遺言書の作成をサポートしてもらえるため、安心です。
Q. 弁護士に、公正証書遺言の証人を依頼することはできますか?
可能です。公正証書遺言には2人以上の証人が必要ですが、遺言書作成のサポートを依頼した弁護士に立ち会ってもらえれば、証人選定の手間を回避でき、公証人の質問にも的確に答えてもらえます。証人の日当として、1万円程度の費用がかかるでしょう。
8. まとめ 遺言作成の相談は弁護士がおすすめ
遺言書作成の際は、専門家の力を借りると、自分で対応するよりスムーズに適切な内容の書面に仕上げられます。いくつかの士業がある中で、やはりもっとも頼りになるのは弁護士といえるでしょう。迷ったときには、まずはお近くの弁護士事務所で相談を受けてみてください。
(記事は2025年12月1日時点の情報に基づいています)
お近くの相続対応可能な弁護士を探す
北海道・
東北
関東
甲信越・
北陸
東海
関西
中国・
四国
九州・
沖縄